おすすめムービー
霊性、および宇宙の真理という観点から、参考になる映画をピックアップしました。これらに興味のない方にとっては、まったく退屈かもしれません。
この純粋さ、この気高さ、この力強さ。アッシジの聖フランチェスコの物語

ブラザー・サン シスター・ムーン

監督:フランコ・ゼフィレッリ
アメリカ西海岸の都市サンフランシスコ(San Francisco)。この都市名は、Saint Francesco(聖フランチェスコ)を英語読みにしたものです。
『ブラザー・サン シスター・ムーン』は、中世イタリアの聖人、アッシジのフランチェスコが真理に目覚めていく過程を、クレアとの恋、仲間との友情、父親との葛藤、権力との対峙などを複合的にからませながら、詩情豊かに描いた作品です。監督はオリビア・ハッセーのあの『ロミオとジュリエット』を撮ったフランコ・ゼフィレッリ。
この作品は、ストーリーだけを追って見たとしても、心を打つ素晴らしい映画に仕上がっています。しかしそれだけではありません。こうした詩的なシンプルな映画には、ふつう象徴的な意味合いがたっぷり入っているものです。それらの記号を見つけると、この映画の価値がさらに深く理解できます。
この映画における重要な記号は次の3つ。
(1)ヒバリ
(2)服(特にコート)およびその色
(3)冠
(1)のヒバリは自由、(2)の服は富、(3)の冠は権力をそれぞれ象徴しています。この記号を読み解きながら見ると、この映画が、単なる伝記映画ではないことが解ります。
アッシジのフランチェスコは、今日こそキリスト教会の中の聖人と言われていますが、正統派から見れば全くの異端でした。フランチェスコは、教会が示す権威や富が、真のキリスト意識とはかけ離れていることに気づいていました。
彼はそれらに反抗し、真のキリスト意識のもとに生きようとしたのです。その純粋さ、気高さ、力強さ。この映画は、それを、先に挙げた記号を巧みに使って見事に表現しています。
偽物が正統とされ、本物が異端とされる状況は、今も何も変わりありません。
「王冠を小鳥の巣にしなさい」「王位と指輪を川に捨てれば、新しい色の輝きに気づく」これらの言葉も、現代にそのまま投げかけられています。
進化の進んだ他の星から、地球人の覚醒を援助しに来る宇宙人の物語

美しき緑の星(La Belle Verte)

監督・脚本・主演:コリーヌ・セロー
この映画は、ユニバーサル・メンバーである宇宙人が、地球人の「目覚め」を援助するためにやって来て、進化の遅れた地球人を相手に孤軍奮闘するというストーリーをダイレクトに扱ったものです。ユニークなのはコメディ仕立てになっている点で、この結果、作品テーマの要点のみが非常に解りやすくまとめられています。
タイトルの『美しき緑の星』(原題は「美しき緑」)とは、地球よりも遥かに進化した別の惑星のこと。この星では機械文明やハイテクの時代がとっくの昔に終わっており、人々は、自然と調和した、素朴で自由で平和な暮らしを営んでいます。テレパシーが使えるので、他の人を騙したり、はかりごとを企てたりすることはできません。分かち合いの精神が当たり前のようにあり、物事はすべて全員参加の話し合いで決められています。
この星には「星外派遣」という留学制度があり、その募集をする時期が来たのですが、他の星への応募者はたくさんいるのに、なぜか地球だけは誰も行きたがりません。それは、地球文明が粗野で非常に遅れているためです。けれども、ミラという一人の女性が、勇気を出して応募に手を挙げます。これには訳があり、ミラは実は地球人との混血だったのです。
さて、そうして訪れた地球で、ミラは様々な文明格差に愕然としてしまいます。見どころは、ミラが駆使する「接続解除」という超能力。これを浴びた人間は、一瞬で社会のとらわれから解放され、本来の自分に返ってしまうのです。本来の自分とは、嘘のない、素直で、自由を謳歌する自分です。その姿は、既存社会からすれば大層クレイジーに見えるのでした。
「死後の世界」の真実を知る者たちの邂逅

ヒア・アフター

監督:クリント・イーストウッド
この映画は「死後の世界」を題材にしています。タイトル名の『HEREAFTER』には、「この世の先」という意味があるようです。主な登場人物は3人。一人めは、フランス在住の女性ジャーナリスト、マリー・ルレ。二人めは、イギリスはロンドンに住むマーカス少年。三人めはアメリカ人の独身男性ジョージです。3人にはまったく接点がありません。この3人のそれぞれの物語が、入れ替わりで進行していきます。
多くの人がたぶん戸惑うと思うのですが、この形式はずいぶん後まで続き、最後の20分になってからやっと3人の物語が一つになります。しかしここで、俄然この形式が効いて来るのです。最後になって繋がるというところに、この映画の隠れた主題が表現されています。つまり、一見、何の接点もないと思われた状況の奥に、実は最初から互いを引き寄せ合う糸が存在していたということです。
その糸とは、「死後の世界」についての真実を知りたいという欲求です。マリーは、休暇で訪れた東南アジアのリゾート地で、スマトラ島沖地震の大津波に呑み込まれ「臨死」を体験します。マーカス少年は、双子の兄を自動車事故で亡くしてしまいます。その事故は自分の身代わりとなって起きたものでした。ジョージは、「霊能者」としての特異な才能を持っていたのですが、何でも「見えてしまう」自分に疲れ切っていて、今ではすっかり足を洗っています。
このように、3人が共に、三様の体験をしたことの奥にある、本当の「意味を知りたい」という強い欲求を持っていたのです。ここが、この映画のポイントです。普通の人ならば、一時の気の迷いということで処理したり、単なる偶然で済ませたり、オカルティックな話題に終始したりして、それで終わってしまいます。ところが、この3人はそれでは満足しなかったのです。周囲の人たちからは当然、変なやつだと疎んじられます。しかし、3人はその視線を超えて、真実、本物、真理を追求し続けたのです。
このような背景があって、3人が最後に出会うのです。その瞬間、それまでは周囲に誰も理解者がいなかった3人が、パッと理解し合う。まさに「波動の法則」です。この3人は出逢うべくして出逢ったと言えます。そうして、初めて互いに理解者を得た。ということで、この3人にとっては、喜ばしい結末となったのですが、しかし別の見方をすると、「解る人」というのは最初から決まっていて、解らない人には解らないという状況は、残念ながら変わらないのだ、とも読めるのです。
「心医」の道を貫き通した、16世紀実在の医官ホジュン。その圧倒的献身

ホジュン 〜宮廷医官への道〜

監督:イ・ビョンフン
『ホジュン(許浚)』は、『宮廷女官チャングムの誓い』を始めとして『イ・サン』『トンイ』『馬医』と、次々に大ヒットドラマを連発する韓国テレビドラマ界の巨匠イ・ビョンフン監督が1999年に手掛けた連続テレビドラマ作品です。(全64話)
放映時、韓国では視聴率が60パーセントを超えたと言い、イ・ビョンフン監督はこの作品で、今日に続くヒットメーカーとなったのです。
ドラマは、身分制度が根強く支配した16世紀の李氏朝鮮時代に、妾の子として生まれたホ・ジュンが、医術の道を志し、艱難辛苦を乗り越えて宮廷医となるまでの波瀾万丈を描いています。
韓国宮廷ドラマは、どれも両班(ヤンバン)の派閥抗争を軸に、策謀、裏切りの連続で話しを引っ張っていく展開が多いのですが、この『ホジュン』は初期の作品だったせいか、その部分のウエイトは少なく、むしろ個人的な嫉妬心や、親子の愛情、男女間の愛情をめぐる葛藤を主軸にしている点が特徴です。
視聴率稼ぎのためには仕方がないのでしょうが、私個人としては、策謀や裏切りはもう結構という感じで、そこが少ない『ホジュン』が、イ・ビョンフン監督の作品の中では最も好きです。
このドラマで凄いのは、主人公ホ・ジュンの圧倒的な献身です。最初のうちは名声や安易な道を選ぼうとしたこともあったのですが、生涯の師となるユ・ウィテの叱責を受けてからは大反省し、宮廷に上がっても「心医」の道を貫こうとするのです。その気高さに惹かれて、多くの友が彼の周りに集まり、ついに最高権力にまで上り詰めます。
しかしホ・ジュンは、そこに安住することなく、民衆のもとに積極的に出て疫病の治療に当たり、最後は自身も感染して死んでしまうのです。生涯を献身に捧げ尽くした一人の医官。後には、そういう人物がいたという思い出しか残らないのです。
このドラマでもう一つ凄いのは、医官が持つ具体的な診断技術です。今では東洋医学はすっかり駆逐されてしまいましたが、患者に触診もしないし目も合わせないで、コンピュータ上のデータをもとに診断をしている現代の医者と、どっちがよい医者なのだろうかと思うのです。
ホ・ジュンを演じたチョン・グァンリョル氏は地味な役者ですが、とても上手く、この役を好演しています。
生命とは何か。 その意味を圧倒的な映像によって表現した壮大な叙事詩

ボヤージュ・オブ・タイム

監督:テレンス・マリック
この映画は、観る人を確実に選ぶことでしょう。ストーリーも無く、登場人物がいるわけでもない、映像による壮大な叙事詩と思ってもらえればよいと思います。
テーマにしているのは「生命」。それが、現在のクリアな映像技術を使って、これ以上ないという多種多様なイマジネーションの連続によって表現されています。
監督は、『天国の日々』『ツリー・オブ・ライフ』『シン・レッド・ライン』などの作品で名高いテレンス・マリック。ブラッド・ピットとショーン・ペンが出演した『ツリー・オブ・ライフ』にも、一部、同じような神秘的な映像が使用されていましたが、この『ボヤージュ・オブ・タイム』は、その部分を全編に拡大したといった感じです。
この作品の何が凄いかと言えば、アセンションに近づいた人には、身の回りの自然や宇宙が、実際にこのように見えるということです。空や、森や、草花や、虫たちの営みの奥にある「生命」の輝きが見えるのです。
その意味で、それが解る人にとっては、この映画は、懐かしさや安らぎや感動をもたらすでしょうが、解らない人にとっては、退屈極まりないものとして映るでしょう。
ナレーションをケイト・ブランシェットが務めています。
10の冪乗で宇宙を捉えるという発想は「霊性密度」の構造を正しく映す
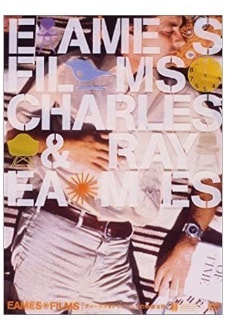
POWERS OF TEN
制作・監督:チャールズ・イームズ/レイ・イームズ
このDVDはイームズ夫妻の映像作品を集めたものです。インテリアにお詳しい方なら、イームズの名を聞いてピンときた方もおられるでしょう。そう、あの有名なの作者と同一人物です。イームズ夫妻は非常に才能豊かな人たちで、家具だけではなく、建築やこうした映像作品も多数残しています。
さてこの作品集で注目したいのは『POWERS OF TEN』という作品です。タイトルにあるPOWERSは「力」の意味ではなく「冪乗」という意味です。したがってこれは「10の冪乗」というタイトル名の作品です。
そのタイトル通り、芝生に寝転んでいる人物の姿から、10倍ずつ遠ざかっていったときに世界はどう見えるのか、逆に10倍ずつ近づいていった時にどう見えるのか、それをCGがなかった時代に脅威の映像技術で創り出しています。10の冪乗で宇宙を捉えるという発想は、大橋正雄氏も取り組んだものであり、その直感は「霊性密度」の構造を正しく表しているという点で特筆に値します。
イームズ夫妻はこの作品に並々ならぬ意欲を見せ、白黒パイロット版、白黒版、カラー版と、何度も再映像化に取り組んでいます。貼付したものは1977年版のカラー作品。
日本語の吹替がついた動画もありますが、画質、音質があまり良くありません。https://youtu.be/paCGES4xpro
CGを駆使したリメイク版もいくつか作られているようです。
https://youtu.be/8Are9dDbW24
https://youtu.be/44cv416bKP4
オードリー演じる尼僧を通して描く、強い意志を持つ女性の自立と旅立ち

尼僧物語

監督:フレッド・ジンネマン 主演:オードリー・ヘップバーン
この映画のテーマをひとことで言えば、「芯のある女性の自立と旅立ち」と言えるでしょうか。タイトルだけを見ますと、オードリー演じるシスターの信仰生活を描いた物語のように感じるでしょうがさにあらず。むしろ信仰の否定を描いていると言っていいと思います。
医師の家庭に生まれたガブリエル(オードリー)は、父の仕事を手伝いながら着々と医療技術を習得し、ついにはアフリカのコンゴへ行って医療活動をしたいという夢を抱きます。
これには、人々の役に立ちたいという強い意志があってのことなのですが、そうして選んだ道がカトリックの修道院に入ることだったのです。つまり最初の時点では、ガブリエルが想い描く理想と、尼僧生活は完全に一致していたのです。
そのようなわけで、厳格な修道院の掟にも堪え、持ち前の優秀さを示すのですが、コンゴへ行きたいという彼女の希望はなかなか適えられず、やっと行けたと思ったら、今度は自身が感染症で倒れてしまうのです。
結局、ガブリエルは道半ばで本拠地のベルギーに舞い戻って来るのですが、しだいに修道院での信仰生活に疑問を持つようになるのです。彼女の奥底に芽生えたものは、自分の自由意志を制限する「信仰」という名の権威に対する疑問だったのではないでしょうか。
修道院にいて、尼僧として働いている限りは、彼女はつねにこの権威の評価を受けることになります。けれども、この構造自体がバカバカしいと気づいたとたん、彼女は当初の意志をあっさり捨てるのです。これには大変な勇気が必要だと思いますが、持ち前の気丈さで、ガブリエルはそこをジャンプするのです。
ラストショットは、修道院の裏口の開け放れたドアから、スーツケース一つ下げて去ってゆくガブリエルを長回しで映しているのですが、それまでのセット撮影から、ドンデン返しで一気に現実の雑踏に出て行く姿をワンショットで見せ、彼女の自立と旅立ちを極めて象徴的に描いています。
ここで学びとしたいのは、この映画は確かに修道院生活を描いてはいるのですが、彼女が飛躍する瞬間に、それまでの洗脳が解けたということ。これは一般社会のあらゆるシーンでも言えることです。
また、世俗というものは確かに汚いものですが、そこから隔絶した場所にいて、自分を高みに置いてはならないということです。世俗の中にいて、なおかつ飛躍した生き方をするのでなければ錯覚に陥ってしまうということも、この映画は教えてくれています。
前半の修道院生活での決まりごとの描写も興味深く(宝塚音楽学校のように、廊下の端を歩くなどがある)、オードリーの尼僧スタイルも清楚で、演技にも見応えがあります。
信仰者が持つ特有な歪みを赤裸々に描き、そこからの解放と救いを示した傑作

おとうと

監督:市川崑 出演:岸恵子、川口浩、森雅之、田中絹代
幸田文原作の『おとうと』は、自伝的要素を多分に含んだ小説で、作家の父(露伴がモデル)、クリスチャンの継母、後に結核で死ぬことになる弟、という家族設定は、幸田家をそのまま映したものです。市川崑監督による映画『おとうと』は、姉のげん役に岸恵子、弟の碧郎役に川口浩、父に森雅之、継母に田中絹代という芸達者な布陣で、一家族の生活のあり方を通して、生きることとは何か、愛することとは何かという、人間にとっての根源的なテーマを、見事に描き出しています。
この作品の凄いところは、テーマが一つではなく、考えさせられる点が幾層にも重ねられていて、それでいて破綻していないという重厚さです。表向きは、そのタイトルが示しているように、弟思いの姉の奮闘物語となっているのですが、その奮闘ぶりの下敷きとなっている、青春期にありがちな弟の苛立ち、継母の冷淡さ、クリスチャンとしての信仰がもたらしている歪み、社会の中枢にいる大人たちの凝り固まった価値観、といった背景要素が、単に背景とは言えない重みを持っているのです。
その目で見ますと、むしろ姉弟愛の方が狂言回し的な背景要素であって、この映画のメインテーマは、《信仰者だからこそ持つ歪みと、そこからの解放》を扱った映画だとも読めるのです。そして、赤裸々に描かれている「信仰者が持つ特有な歪み」(これは、自分たちの信仰だけが正しいと思うことによって生じる、他者をコントローしたいという意識)は、今日においても、いささかも変わることがないように思えます。
映画は、最後に弟の死の場面でエンディングを迎えるのですが、しかしここに、ドンデン返しとも言うべき救いが用意されています。継母役の田中絹代が最後に語った言葉に、この映画の真のテーマが表されているように思います。

「神」の存在を“信じる”者と、実証主義ゆえに保留する者との、皮肉な逆転劇

コンタクト (CONTACT)

原作:カール・セーガン 監督:ロバート・ゼメキス 主演:ジョディ・フォスター
この映画は、不思議な趣きを持ったSF作品です。導入からクライマックスまでは、現代科学の実証主義的な面を下敷きにして進んで行きながら、クライマックスになると、あっと驚く結果へと導かれます。しかも、この結果が示している内容というのが、“因の科学” から見て、決して荒唐無稽とは言えないものになっている点がとてもユニークです。
ジョディ・フォスター扮するエリナー・アロウェイ(愛称エリー)は、少女時代から天文学に大きな関心を寄せ、長じた今はSETIプロジェクトの代表的研究者となっています。SETIというのは、地球外知的生命体探査(Search for extraterrestrial intelligence)のことで、平たく言えば、宇宙人探し。そのせいで、エリーは研究者仲間からは小馬鹿にされ、研究費を出してくれるスポンサーもなかなか見つかりません。
ところが、ハデンという怪しげな大富豪が、どういうわけかこれに興味を示し、出資してくれることになります。エリーは、さっそくニューメキシコにある電波望遠鏡群を借りて探査を開始します。しかし成果はなかなか上がりません。数年が空しく過ぎたある日、ついに琴座のベガ星付近から発せられた信号をキャッチ。それは明らかに意図を持った信号でした。これを解析するうちに、エリーは、やがて知的生命体からのものと思われる図面入りのメッセージをその中に見い出すのです。
この図面に描かれた巨大装置の用途は不明でしたが、俄然、関心を持ったアメリカ政府が介入するところとなり、実際にこれを制作するプロジェクトが開始されます。どうやらそれは、時空間を超えた航行装置のようでした。紆余曲折を経てその搭乗員となったエリーは、時空を超え、遂に地球外知的生命体との遭遇を果たします。ところが、そこで出会った生命体は、エリーの想像を超えた驚くべきものだったのです。というのがストーリー。
さて、この映画で注目していただきたいのは「神」の存在の「実証」という点です。エリーは、科学者らしいプラグマティスト(実証主義者)で、曖昧さや嘘は嫌います。ですから「神」の存在や、それへの「信仰」ということについては態度を保留していて、それがキリスト教国であるアメリカ社会から見れば非難の的となっています。
ところが、エリーが、地球外知的生命体との遭遇体験を(実証的に)証言すると、なんとこれが誰からも信用されないのです。結局、実証なしに「神」の存在や「信仰」を盲目的に信じている者たちというのは、その枠組みを超えるものは決して認めようとはしないのです。この実情は、現実をとてもよく映していると思います。
同じようなプロットですが、『メッセージ』(原題:Arrival)ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督作品もお勧めです。
「宇宙は一つ」であることを、圧倒的なリアリティで感じさせる異色SF映画
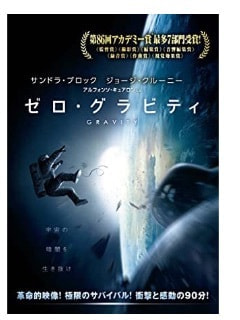
ゼロ・グラビティ(原題:GRAVITY)
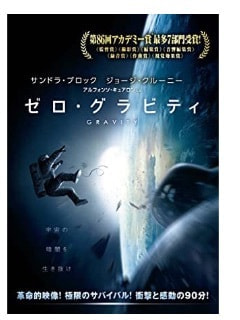
監督:アルフォンソ・キュアロン 出演:サンドラ・ブロック、ジョージ・クルーニー
この作品を監督したアルフォンソ・キュアロンは、この映画を実現するために、自分が想い描く世界を描き切るためには、着想を得てから、CG技術が発達するのをしばらく待たねばならなかったと述べています。その通り、この映画の圧巻は、宇宙空間のリアリティで、劇場公開時には3Dで公開されたのですが、本当に、広大な宇宙にポツンと自分だけがいる感覚にさせられるのです。
キュアロン監督は、この映画の狙いについて、「人生の困難をいかに克服するか」だと述べています。そして、それを描くための設定として、頼れるものなど何もない極限の世界である「宇宙空間」というものを選んだのでしょう。
お話は、宇宙空間で起こった絶体絶命のピンチから、いかにして生還するかというシンプルなものです。しかしここに、霊的なニュアンスが暗喩的にいくつも被せられている点が、この映画を、単なるSF映画としては片づけられないものにしています。
先ず、主人公のライアン(サンドラ・ブロック)が、窮地を脱するべく乗り込んだソユーズが向かった先は、どこであったか? 中国の宇宙ステーションであるところの、その名も「天宮」です。この時、燃料切れを知って絶望するライアンに、起死回生のアイデアを授けてくれるのが、同僚のマット・コワルスキー(ジョージ・クルーニー)の幻でした。彼は、その以前に、ライアンを助けようとして自分の命を犠牲にしていたのでした。そのマットが、再度助けようとして現れるのです。
彼女はそこで、マットを通じて天啓を受け取ります。そして希望を取り戻し、「神舟」(つまり神の舟)に乗ることによって、緑の大地である地球に生還を果たすのです。ラストでは、まるで羊水のような湖底から、ライアンが、赤子のような形で力強く地上に再生する姿が描かれます。ここに、あのSF映画の金字塔『2001年宇宙の旅』が示したテーマと、同じものが読み取れます。実際、『2001年宇宙の旅』にオマージュを捧げたと思われるショットも見られます。
『ゼロ・グラビティ』は、これらを通じて、毎日の困難をいかに克服するか、という日常生活に対する暗喩とともに、同時に、その裏にもっと深い暗喩を忍ばせていると言えるでしょう。それは、「宇宙は一つ」ということ。
広大な宇宙に一人ぼっちという、最初の心細さの方が実は幻影なのであり、自分はいつでも宇宙にしっかりと抱かれていたのだと。宇宙から生まれて、宇宙に帰り、また再生するのだということ。だから、マットの援助は幻だったのではなく、マットはずっと生き続けているのだということ。こうした大テーマを、この映画は宿していると思います。